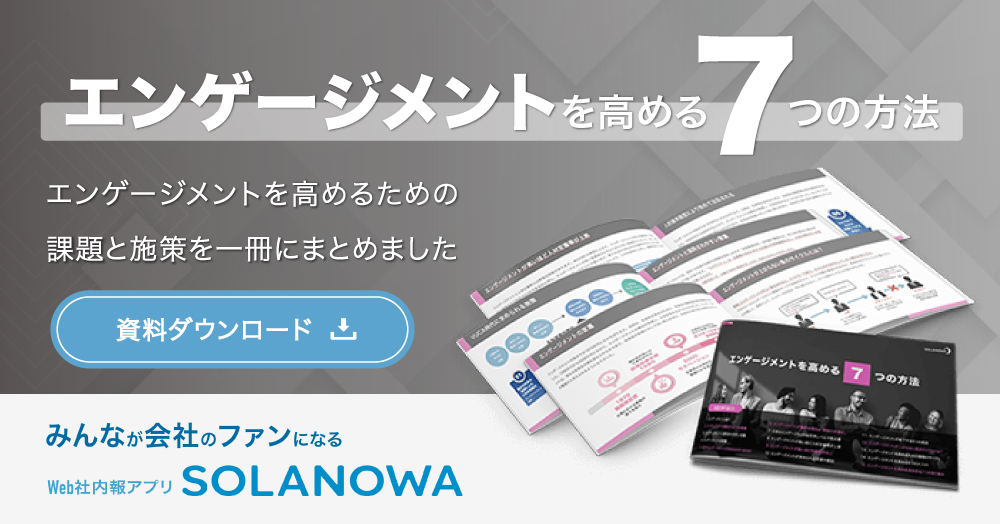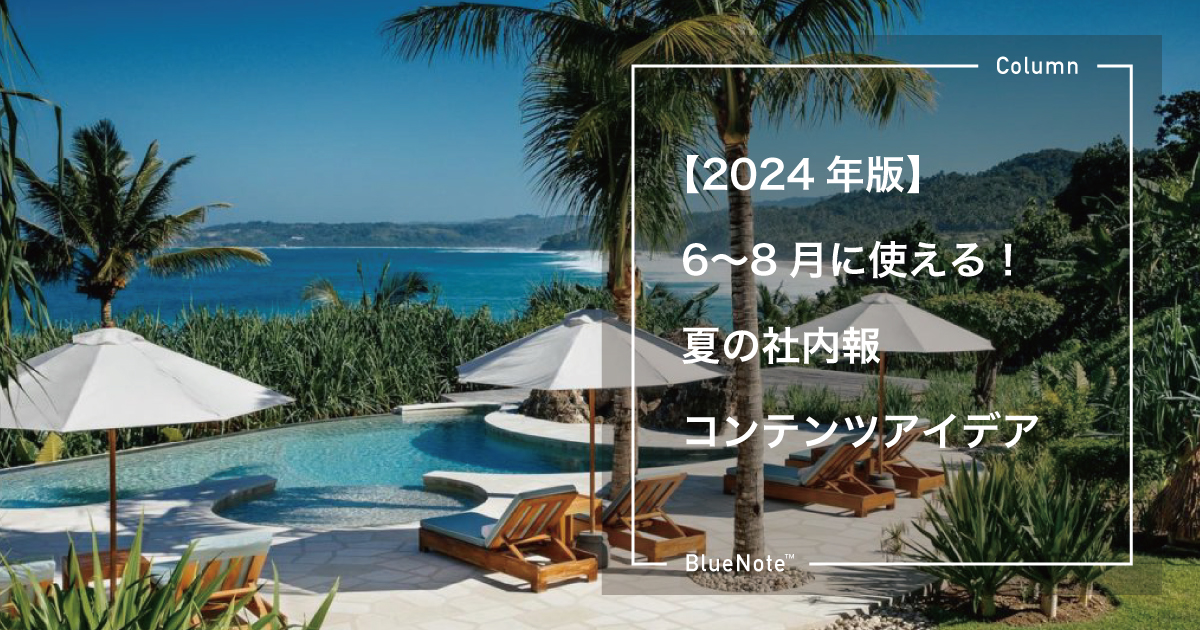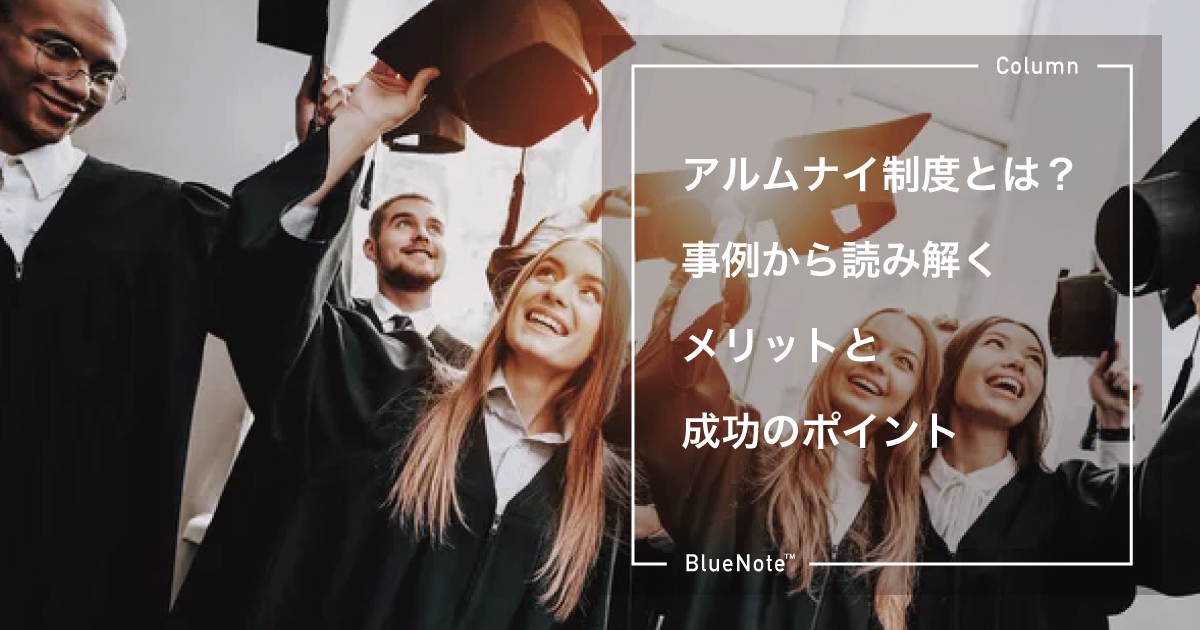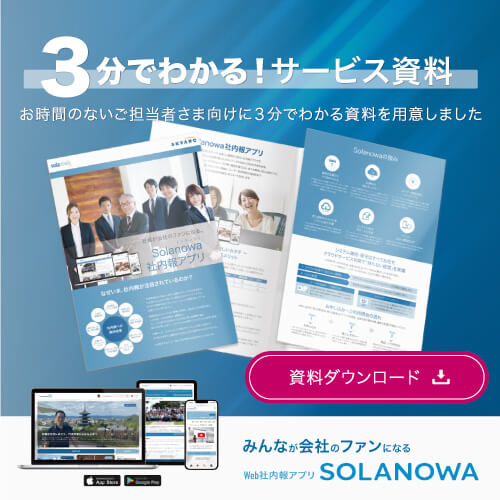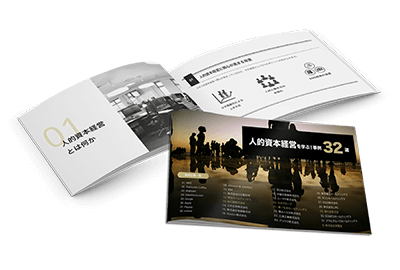2025年、日本は団塊の世代全員が75歳以上となる超高齢社会に突入します。
この「2025年問題」は、雇用、医療、福祉など社会のあらゆる分野に多大な影響を与え、企業の競争力にも大きな影響を与えると予想されています。
2025年問題はどの業界にも関係し、対策を怠れば将来的に競争力を失う可能性があります。
そして、この2025年問題は一時的な現象ではなく、その後も高齢化は加速していくため、長期的な視点での対策が重要です。
そこで今回は、2025年問題とは何か?社会や企業に与える影響や、今からできる対策などについてまとめました。
目次
●2025年問題とは?
●2025年問題の背景
●「2025年の崖」との違い
●「2040年問題」との違い
●2025年問題が社会に与える影響
・労働人口の減少
・社会保障費の負担の増大
・医療・介護の体制維持が困難になる
・ビジネスケアラーが増える
●2025年問題によって起こる企業や従業員への影響
・人材確保が困難になる
・人的資本の成長率が鈍化する
・既存体制の維持が困難になる
・後継者不足や技術継承に関する問題
●2025年問題が各業界にもたらす影響
・医療・介護業界
・建設業界
・運送業界
・飲食業界
・保険業界
・IT・情報サービス業
●2025年問題に向けて企業ができる5つの対策
1:働きやすい職場環境の整備
2:外部のリソースの活用
3:既存システムの見直しとDX推進
4:公的支援やM&Aによる事業継承の検討
5:ベテランの技術やノウハウの継承
●まとめ
2025年問題とは?
2025年問題とは、1947~1949年生まれの「団塊世代」の人が、75歳以上の後期高齢者となることによって引き起こされる、さまざまな問題のことです。
この団塊の世代の人数は約800万人と言われていますが、2025年にはそのすべてが後期高齢者となるため、日本は国民の5人に1人が後期高齢者という「超高齢化社会」を迎えることになります。
2025年問題は社会のあらゆる分野に深刻な影響を与えると予想されています。
日本の人口は2008年にピークに達し、その後の2010年以降、急速な人口減少が続いています。
さらに、若年層の非婚化や晩婚化が進むことで少子化のペースが加速しており、この人口減少の傾向は当分の間続くと見られています。
また、2025年には、70歳以上の経営者を持つ中小企業が約245万社に増加し、そのうち約127万社では後継者が未定のままです。
この後継者不在問題が解決されない場合、約650万人の雇用が失われ、GDPは約22兆円減少すると予測されています。
2025年問題の背景
2025年問題の背景には、急速な少子高齢化があります。
65歳以上の人口が全体の21%以上を占める社会のことを「超高齢化社会」と呼んでいますが、日本は2007年に超高齢化社会に突入しました。
その後も高齢化は進行し、2025年には65歳以上の高齢者が国民の約3人に1人になり、75歳以上の後期高齢者が約5人に1人になると予測されています。
同時に、出生率の低下により若い世代の割合が減少し、労働力人口の減少が課題となっています。
「2025年の崖」との違い
2025年問題と2025年の崖は、いずれも2025年頃に日本の社会に大きな影響を与える課題として注目されています。
しかし、2つの課題は異なる側面に焦点を当てているため、混同しやすい点に注意が必要です。
2025年問題は、少子高齢化という社会構造の変化によって、医療・介護、社会保障、経済、地域社会など、社会のあらゆる分野に深刻な影響が出ると予想される問題を総称します。
一方、2025年の崖は経済産業省が提唱した言葉で、デジタル技術を活用した業務改革(DX)を推進しなければ、2025年以降に年間最大12兆円の経済損失が発生する可能性を指摘しています。
企業が2025年以降に直面する経営上の危機に焦点を当てたものだと言えるでしょう。
具体的には、2025年頃にWindows 7やWindows Server 2008などのサポートが終了し、システムの脆弱性やセキュリティリスクが高まることが懸念されています。
「2040年問題」との違い
2025年問題と混同されやすいのが「2040年問題」です。
どちらも日本の社会構造や経済に関わる重要な課題ですが、それぞれ異なる側面を持ちます。
「2040年問題」とは、団塊の世代の子ども世代である「団塊ジュニア世代」が2040年頃に65歳に達することで、高齢者の割合が急増し、同時に労働人口が急減することから、国内経済や社会制度が危機的な状況に陥ると予測される問題を指します。
団塊の世代が後期高齢者となり75歳以上の人口が急増する2025年問題とは異なり、2040年問題では65歳以上の高齢者が最も増加し、社会的影響がより深刻化すると見込まれています。
どちらの問題も、高齢者の増加により社会のすべての分野で既存のシステムを維持することが難しくなるという点では同じですが、2025年問題は高齢化に伴う社会的な課題に焦点を当てており、2040年問題は労働力人口の減少に関連する課題に焦点を当てている点に違いがあります。
2025年問題が社会に与える影響
2025年問題が社会に与える影響とはどんなものがあるのでしょうか?
2025年問題によって引き起こされる具体的な影響は、主に次の4つがあげられます。
・労働人口の減少
2025年問題がもたらす最大の影響は、人材不足の深刻化です。
2025年問題が社会に与える影響のもっとも大きな点が、労働人口の減少です。
団塊の世代が後期高齢者となり、労働力市場からの退場が予想されるため、労働力人口が急激に減少します。
非婚化や晩婚化などにより少子高齢化が加速しており、成人して就業する人口よりも高齢化して退職する人口の方が多い状況が続いており、総務省の推計によると、2025年には、労働人口が約6,440万人まで減少すると予測されています。
これは、1990年代後半と比べて約1,000万人少ない数字であり、経済活動への大きな打撃となる可能性があります。
この人材不足は全ての業種に影響し、中堅・中小企業における後継者不足も深刻化すると言われています。
・社会保障費の負担の増大
高齢者人口の増加は、医療費や介護費などの社会保障費の増加につながります。
厚生労働省の推計によると、2025年には社会保障費が約130兆円に達するとされています。
これは現在のGDPの約2倍に相当し、2017年よりも約30兆円増加したことを意味します。
後期高齢者の医療費は基本的に1割負担であり、残りの9割は現役世代が支えています。
2025年問題により後期高齢者が増加し、医療や介護施設の利用者数が増えることで、社会保険料負担が増大する見通しです。
社会保障費の増加は、現役世代の負担増加や社会保障制度の維持困難などの問題を引き起こす可能性があります。
・医療・介護の体制維持が困難になる
2025年問題は医療や介護分野にも多大な影響があります。
厚生労働省の推計によると、2025年には介護が必要となる人が約700万人になるとされており、これは2017年よりも約300万人増加したことを意味しています。
しかし、人材不足の深刻化は医療・介護分野にも大きな影響を与え、適切な医療サービスの提供が困難になる可能性があります。
さらに、後期高齢者の増加に伴い医療費も増加する見込みです。
財源の限界から、現行の1割負担制度で後期高齢者への医療サービス提供が困難になる可能性が高く、診療報酬の見直しも行われる見通しです。
その影響で病院やクリニックの経営が困難になり、最悪の場合、廃業や閉鎖に追い込まれる施設が増えるかもしれません。
このような状況が重なると、現行の制度の維持が難しくなり、制度全体の見直しが必要となる可能性があります。
・ビジネスケアラーが増える
2025年問題によって、ビジネスケアラーが増えると予想されています。
ビジネスケアラーとは、仕事と家族の介護を両立する人のことを指します。
総務省の調査によると、過去10年間の推移では、2012年から2022年までの間にビジネスケアラーの数が約70万人増加し、年間平均で7万人程度の増加率を示しています。
2025年には、ビジネスケアラーが約700万人になると予想されています。
ビジネスケアラーは、仕事と介護の両立による負担増加や離職などの問題に直面する可能性があり、離職や労働生産性の低下から引き起こされる経済的損失はすでに約9兆円に及んでいることから、この問題は社会全体にとって大きな課題となっています。
2025年問題によって起こる企業や従業員への影響
2025年問題は、企業にも大きな影響を及ぼします。
2025年問題によって起こる企業や従業員への影響は、主に次の4つがあげられます。
・人材確保が困難になる
2025年問題によって、企業は人材確保が困難になると予想されています。
前述の通り、総務省の推計では2025年には労働人口が約7,000万人まで減少するとされており、1990年代後半から約1,000万人減少しています。
労働人口の減少は、企業にとって人手不足という問題を引き起こします。
特に、中小企業は人手不足の影響を受けやすく、事業継続が困難になる可能性もあります。
・人的資本の成長率が鈍化する
2025年問題によって、企業の人材育成が困難になり、人的資本の成長率が鈍化すると予想されます。
人的資本とは、企業の従業員が持つ知識、スキル、経験などの無形の資産を指します。
近年、晩婚化や医療の進歩により、出産年齢が上がる傾向が見られます。
前述のビジネスケアラー以外にも、育児と介護が同時期に発生する「ダブルケア」の家庭が増加しています。
また、10代から20代の若い世代でも、仕事と介護で忙しい親のサポートをする「ヤングケアラー」の存在があります。
こうした状況では、従業員やその家族が介護や家事に追われるため、仕事に集中することやキャリアの発展が困難になる可能性があります。
特に「ヤングケアラー」は、家庭の介護負担により進学や就職の希望を諦めることが懸念されます。
学習機会の減少や非正規雇用の増加により、キャリアの成長に制約が生じる恐れがあります。
こうしたケアラーの問題は社会的な現象であるため、企業全体で見ると影響は大きく、結果として、企業においても人的資本の成長が鈍化する可能性があります。
・既存体制の維持が困難になる
2025年問題によって、企業は既存の体制を維持することが困難になります。
例えば、従来の年功序列制度や終身雇用制度は、労働人口の減少や高齢者の増加によって維持が困難になる可能性があります。
また、冒頭で解説した「2025年の崖」によるシステムのサポート終了や維持管理費の急増リスクや、システムの老朽化に伴うトラブルやセキュリティリスクも懸念されており、2025年以降に年間最大12兆円もの経済損失が発生する可能性が指摘されています。
経済産業省は、これらのリスクに対処するためにシステムの見直しや刷新を推進していますが、このようなシステムの見直しに追いつけない場合、既存の組織体制の維持が困難になるでしょう。
・後継者不足や技術継承に関する問題
2025年問題によって、企業は後継者不足や技術継承に関する問題に直面する可能性があります。
日本の企業や法人の約99%が中小企業であり、その多くが高齢化した経営者や後継者不足に悩んでいます。
少子化の影響で親族内での事業承継が困難になり、後継者が見つからないケースが増加しています。
この状況が続けば、後継者不足による廃業が相次ぎ、中小企業庁の資料によると2025年までに約650万人の雇用、約22兆円のGDPが失われると試算されています。
さらに、建設業や製造業などの技術の継承が重要な業界でも、高齢化が深刻です。
熟練技術者が退職すると、その技術が失われてしまう可能性もあります。
若い世代の育成が追いつかず、ベテラン技術者の定年退職により専門技術の継承が困難になっています。
後継者不足や技術継承の問題は、企業の廃業につながる懸念があります。
2025年問題が各業界にもたらす影響
2025年問題は、各業界に深刻な影響を与えることが予想されています。
ここでは、特に影響が大きいと考えられる6つの業界についてまとめました。
・医療・介護業界
医療・介護業界では、後期高齢者の増加に伴い、慢性疾患や認知症などの治療や介護ニーズが増大する見込みです。
医療機関や介護施設の需要が拡大し、施設の増設や改修が必要とされます。
しかしながら、介護職の人手不足や高い離職率などの課題が深刻化し、適切なサービスの提供が困難となる恐れがあります。
また、高齢者の増加により医療費や介護費の増大も懸念され、社会保障制度の改革が求められ、現状の制度を維持するのは極めて難しい状況と言えるでしょう。
さらに、社会保険料の増加は業界にとっても大きな懸念であり、診療報酬の引き下げなどが実施されれば、経営が困難な病院が増える恐れがあります。
・建設業界
建設業界は、すでに就業者の高齢化が進行しており、若手人材も減少傾向にあります。
2025年以降、団塊世代の大量退職により、建設業界における人材不足がさらに深刻化することが予想されています。若手人材の確保は、業界全体の存続に関わる喫緊の課題です。
術者や熟練工の定年退職により、技術の継承が困難になり、建設プロジェクトの品質管理や工程管理に問題が生じる可能性があります。
さらに、建設業界におけるデジタル化の推進も重要です。
現在、建設業界ではアナログ作業が主流であり、これが労働者の負担増加や生産性の低下を招いています。
デジタルツールの導入と業務プロセスの最適化が必要で、作業を効率化し、若手人材にとっても魅力的な職場環境を提供することが求められます。
・運送業界
運送業界は、2024年4月1日に施行される改正労働基準法による時間外労働規制と、2025年の高齢ドライバーの大量退職という2つの大きな課題に直面しています。
2024年4月1日以降、トラック運転手の時間外労働時間の上限は年間960時間までに制限されました。
これは、ドライバーの収入減少、運送会社の収益減少、運賃値上げ、ドライバーの離職など、様々な問題を引き起こす可能性があります。
2025年には、多くのドライバーが65歳以上となり大量退職が予想されており、人材不足をさらに深刻化させ、物流の停滞や物価上昇などの問題につながる可能性があります。
IT人材不足や古いシステムの使用などにより、運送業界におけるDX推進は遅れていると指摘されていて、配達の合理化が進まず人手不足を補うことができていないことから、人材確保と並行してDX推進による効率化が不可欠です。
・飲食業界
飲食業界は、長時間労働や低賃金などによる慢性的な人手不足という大きな課題があります。
2025年以降、労働力人口減少により、この問題はさらに深刻化する見込みです。
調理スタッフやホールスタッフの確保が困難になり、店舗運営への影響が懸念されます。
人手不足に加え、原材料価格の高騰や消費者の嗜好の変化に対応することも課題となっています。
また、飲食業界の正社員は、学生の退職などによって過度の労働を強いられることが多く、高い離職率が懸念されます。
業界の持続可能な発展のためには、働き方や労働条件の改善が喫緊の課題となっています。
・保険業界
保険業界では、後期高齢者の増加に伴い、医療・介護費と保険金の支払い額が増加し、保険料の値上げが避けられません。
また、後期高齢者の増加と若年層の減少は、新規契約者の減少と保険金支払いの増加を意味することから、2025年問題により、保険業界は売上の大幅な減少が予想されます。
高齢者向けの保険商品開発の困難になり、保険事業の収益悪化が指摘されています。
保険業界は競争力を維持するために、人件費の削減や新規サービスの開発による売上の確保など、コスト削減とイノベーションが不可欠です。
IT・情報サービス業
IT・情報サービス業では、前述の「2025年の崖」の問題が特に深刻です。
既存システムの複雑化と老朽化が進む中、2025年以降、競争力を維持することがますます難しくなるでしょう。
高度なITスキルを持つ人材不足が深刻化し、企業のデジタル化やイノベーションが阻害される可能性があります。
人材不足に加え、サイバー攻撃などのセキュリティ対策が課題です。
経済産業省の推計によると、IT関連産業への入職者は2019年をピークに減少し、2030年には約79万人もの人材が不足すると予測されています。
さらに、IT人材の平均年齢も高齢化しており、ITニーズの増加に対する需給ギャップの拡大も大きな懸念材料です。
課題の解決には企業の採用力が鍵となるため、働きやすい環境を整備し企業の魅力を高める努力が求められています。
2025年問題に向けて企業ができる5つの対策
2025年問題への対応は、企業の存続に関わる重要な課題です。
課題解決に向けて企業が取り組むべき対策は様々ありますが、多くの業界にも共通する5つの対策をご紹介します。
1:働きやすい職場環境の整備
人材不足の解消には、採用活動だけでなく、長期間働ける職場環境を整えることが不可欠です。出産や育児支援に加えて、今後は介護と仕事の両立も考慮する必要があります。
前述の通り、経済産業省の調査によると働きながら介護を行うビジネスケアラーは、2030年には約318万人になると予想されています。
多くのビジネスケアラーが介護と仕事の両立が難しいために離職しており、こうした離職を防ぐためには適切な環境整備が急務です。
さらに、シニア人材を積極的に活用することも大切です。
定年引き上げなどを通じて、高齢者が能力に応じて積極的に働ける仕組み作りも必要となります。
また、個々のライフスタイルに適した雇用形態や、時短勤務やリモートワークを整備するなど、社内全体で多様な働き方への理解を深めることが不可欠です。
2:外部のリソースの活用
人材不足の解消には、社内でのアプローチだけでなく、外部の人的リソースを活用することも有効です。
その一つの手段がBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)の導入です。
BPOは企業の業務プロセスを外部に委託する形態で、例えば経理部門や人事部門の業務を外部専門家に委託することができます。
社内の人員の流動や忙しさの波に左右されず、業務の安定遂行が可能です。
BPOを活用することで、企業はノンコア業務を外部に委託し、社内ではコア業務の人員育成に注力でき、企業の競争力強化につながります。
外部のリソース活用は、人材不足の解消だけでなく、企業の効率性向上や競争力強化にも貢献します。
3:既存システムの見直しとDX推進
労働人口が減少する中で事業を維持するためには、生産性の向上が不可欠です。
具体的には業務の洗い出しや可視化を行い、不要なプロセスや非効率なプロセスを見直すことが重要です。
さらに、IT技術を活用したDXの推進も効果的です。
近年では、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)などの技術が開発され、人が従来パソコンで行ってきた業務プロセスを自動化できるようになりました。
ような技術の導入により、作業の自動化や効率化が可能となり、従業員はより価値の高い業務に集中できるようになります。生産性向上の期待が高まっています。
4:公的支援やM&Aによる事業継承の検討
中小企業における後継者不足は深刻であり、親族や従業員の中から後継者を見つけることが難しいため、最近では、M&A(第三者承継)による事業譲渡が増加しています。
中小企業庁は、後継者不足に悩む企業に対し、M&Aのマッチング支援や事業承継計画の策定支援などを行っています。
その1つである「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)の施行により、企業は事業承継の負担を軽減するための様々な公的支援を受けられるようになりました。
事業承継には時間的なスピード感が求められます。
通常、後継者の育成を含めると、事業承継には5~10年程度の準備期間が必要です。経営者の平均引退年齢が70歳前後であることを考慮すると、経営者が60歳になった時点で準備を開始する必要があります。
事業承継は短期間で行えるものではないため、従業員の雇用を守るためにも早めに対策を講じることが重要です。
5:ベテランの技術やノウハウの継承
中小企業にとって、ベテランの技術者から若手への技術やノウハウの継承は重要な課題です。
この継承がうまく進まないと、企業の競争力や業務の品質に影響を与える可能性があります。
定期的な技術研修やメンタリングプログラムの導入など、若手がベテランから学ぶ機会を確保することが重要です。
また、継承先に複数の人材を配置することで、リスクを分散し、技術の継続性を確保することも大切です。
さらに、ベテラン技術者の知識やノウハウをマニュアルや動画などの形で蓄積し、共有する仕組みを構築することも有効で、失われることのない知識の記録や伝達が可能となります。
技術の継承をサポートするITツールやプラットフォームの活用も検討すると良いでしょう。
まとめ
2025年問題は、労働人口の減少や社会保障費の増大など、多岐にわたる社会的影響をもたらすと言われており、企業や従業員にも様々な影響が及びます。
しかしながら、2025年問題は、単なる労働人口減少の問題ではなく、社会全体に大きな変革をもたらすパラダイムシフトです。
企業はこの変化を脅威と捉えるのではなく、未来へのチャンスと捉え、積極的に改革に取り組む必要があります。
働き方改革、DX推進、外部リソースの活用、公的支援の活用、事業継承の検討、ベテランの技術継承など、様々な対策を積極的に実行することで、2025年問題を乗り越え、持続的な成長を実現することができます。
重要なのは、こうした取り組みを一時的な方法で行うのではなく、長期的な戦略を練り、着実に実行することです。
2025年問題は一過性の現象であり、その後にはピークを迎える2040年問題が待ち受けています。
企業は将来を見据え、さまざまな準備を整える必要があります。
労働力人口の減少に伴い、人材の確保がますます困難になる中で、従業員が安心して働き続けられる職場環境を整えることが重要になってきています。
企業が競争力を維持するためには、限られた労働力をより効率的に活用することが重要です。
そのためには、従業員一人ひとりが高いモチベーションを持ち、能力を最大限に発揮できる環境が必要になります。
2025年問題を乗り越え、繁栄する企業となるためには、従業員エンゲージメント向上を経営戦略の柱の一つとして位置づけ、積極的に取り組んでいくことが不可欠といえるでしょう。
本コラムで紹介した内容を参考に、貴社における2025年問題への取り組みと自社に合った従業員エンゲージメント向上の施策を検討してみてはいかがでしょうか。